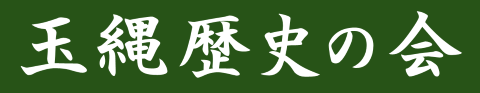令和6年(2024年)11月4日(月・祝日)、『神奈川県立歴史博物館 学芸部の梯 弘人 先生』にお越しいただき、『戦国大名北条氏にとっての西相模・伊豆地域の重要性』についてご講演いただきました。
ポイント
● 2つ性格を持つ地域
相模川以西の相模国および伊豆国は『北条氏の直轄支配地域』であり、北条氏当主を支えた地域と領国西端の地域という2つの性格に焦点を当たった。
● 北条氏の領国支配体制
<相模川以東の領国の拠点城郭>一族・重臣を配置して分割統治を行った。
・玉縄城(相模国鎌倉郡):玉縄北条氏
・三崎城(相模国三浦郡):北条氏規(氏康四男、氏政・氏照同母弟)
・津久井城(相模国津久井郡):相模内藤氏
・小机城:北条一族
<西相模・伊豆地域>郡代として当主の直属軍団を配置。北条氏の命令下で公事(税)徴収。
・相模西郡:石巻氏(馬廻衆・小田原)
・相模中郡:大藤氏(諸足軽衆・秦野)
・伊豆国:清水氏、笠原氏(伊豆衆・三島、韮山)
● 当主の直轄支配
小田原衆所領役帳(北条家文書・神奈川県立歴史博物館蔵)には、北条家臣の領地とその所領規模が記されており、台帳所領規模を基に引率する軍勢の人数が定められた。
<所領役帳の内容>
・北条家臣:馬廻衆 石巻下野守(家貞)
・所領の場所:西郡 飯田壱岐分(小田原市)、豆州 櫟山(伊豆市)、中郡 土屋内五分一(中井町)
小机 多々久(横浜市)など、合計 三百壱貫文(三百壱貫文分の奉公)
<公事(税)の取り立て:大道寺盛昌から江梨鈴木氏に宛てた書状での公事>
・鈴木氏の所領である江梨(静岡県沼津市)に『やとい夫』の負担を命じる
・命令は郡代からの使者(触口)から伝達された
・江梨は不入と主張し、公事免除の経緯を説明(早雲寺殿様が石脇(焼津市)にいた時から当家は協力)
・これまでの事情について、大道寺から重臣の遠山・笠原氏へ伝える
※不入権(免税)に関する実例資料として非常に興味深い。
● 西相模・伊豆地域を巡る政治状況
天文6年(1537年)の河東一乱から天正18年(1590年)の小田原合戦まで、50年余りの間に北条氏の領国西端地域では様々な動きがあった。
<主な出来事>
・天文6年(1537)河東一乱
『小田原天文記(快元僧都記)には、同年6月に北条軍が駿河へ出陣して勝利を得たとの記述。
・天文23年(1554年) 三国同盟成立
・永禄11年(1568年)武田信玄の駿河侵攻、三国同盟崩壊
・永禄12年(1569年)武田信玄の小田原城攻撃、三増合戦
小田原に攻め込んだ信玄を退け、撤退する武田軍を三増峠で追撃。武田軍の勝利と言われるが、北条氏照は書状にて「信玄を取り逃がした」と表現。
・元亀2年(1571年)武田氏と同盟が復活
・天正7年(1579年)武田氏との同盟崩壊
上杉氏の家督を巡る争い(御館の乱)に介入し、北条氏政は弟・上杉景虎を支持。武田勝頼は上杉景勝を支持したため、武田氏との同盟はまたも崩壊。
注)以降、徳川の駆け引きが活発となる。
・天正10年(1582年)武田攻め、天正壬午の乱
織田信長により武田氏は滅亡するが、本能寺の変で信長が横死すると、武田領が争奪の対象に。北条・徳川・上杉三氏の争いが起こる(天正壬午の乱)
・北条と徳川の間で同盟成立。家康の娘が氏直に嫁ぐ。
・天正18年(1590年)小田原合戦
豊臣秀吉が20万を超えるという大軍勢で小田原城を包囲。北条氏は約3ヶ月の老嬢の後に降伏。家康が韮山城に籠る北条氏規に対し、降伏を勧めるために送った書状が残っている(2人が今川氏の人質だった頃からの旧知だったというエピソードもあり)
講演後記
戦国時代にありながら、北条氏は合理的な行政機構と地域分担を確立し、安定した領国運営を実現したと感じる。秀吉に滅ぼされず、北条氏の統治が長く続いたならば、どのような世になっていただろう。
大きな意味で北条氏の『本丸』であり、紛争の絶えない『領国の西の際』でもあった『西相模・伊豆地域』の重要性を多面的に知ることができた講座だった。また、その裏付けとなる古文書の紹介もしていただき、納得感も非常に高かった。
梯先生のご講演は今回が第1弾であり、年明けの3月には今回の続きとして、同じく北条氏を題材とした講演を予定している。ご多忙な梯先生にはお手数をお掛けしてしまうが、今から楽しみでならない。梯先生、次回も宜しくお願いいたします。
 古文書の解説が非常に分かりやすい梯先生 |