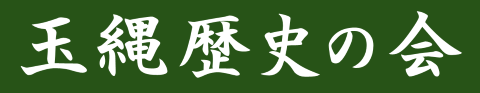令和7年(2025年)6月8日(日)、歴史水先案内人である『横浜市人聖殿郷土資料館 相澤 竜次 先生』をお招きし、『複雑すぎてわからない?~室町時代の関東争乱~』について、ご講演いただきました。
ポイント
● 鎌倉幕府の成立と崩壊:武家政権の始まりと終焉
鎌倉幕府は源頼朝によって創設され、武士による政権運営が始まった。承久の乱(承久3年・1221年)以降、北条義時を中心とする執権政治が確立。北条氏による支配は100年以上続き、御家人制度を基盤とした封建体制が整備された。
しかし、元寇(文永11年・1274年、弘安4年・1281年)では、外敵に対する防衛戦であったため、戦後の恩賞がなく、御家人の不満が高揚。これが幕府の求心力低下につながり、宝治合戦・霜月騒動などで有力御家人が没落。長崎氏に代表される御内人が実権を握り、執権政治は腐敗していった。
元徳3年(1331年)、後醍醐天皇は討幕を企て挙兵(元弘の乱)。幕府の有力御家人だった足利尊氏が反幕府勢力に加わり、六波羅探題を攻略。新田義貞も鎌倉へ進軍し、鎌倉幕府は滅亡した。
● 建武の新政と南北朝の混乱:公家政権の限界と武家の再興
後醍醐天皇は建武の新政を開始し、公家中心の政治を復活させたが、武士への恩賞不足や指揮系統の混乱により短命に終わってしまう。これにより、南北朝時代が始まり、吉野に南朝、京都に北朝が並立する60年の混乱が続く。
この時期、足利尊氏が実権を握り、征夷大将軍となって室町幕府を開設。鎌倉には『鎌倉府』が設置され、尊氏の子孫が『公方』として関東を統治。『関東管領』には上杉氏が任命され、山内・扇谷・宅間・犬懸などの分流が台頭した。
南北朝の対立は、皇位継承問題や荘園支配を巡る争いを背景に、全国的な内乱を引き起こし、地方の武士団が台頭する契機となっていく。
● 関東管領と上杉氏の分裂:家宰の台頭と地域支配の複雑化
関東管領職は山内上杉氏が独占し、他の分流は補佐役として活動。長尾氏や太田氏などが『家宰』として台頭し、関東の政治構造は複雑化していく。
犬懸上杉氏による『禅秀の乱』(応永23年・1416年)では、鎌倉公方・足利持氏との対立が激化。『小栗満重の乱』(応永29年・1422年)では、北関東勢力が反乱を起こし、関東の分裂が進んだ。
『永享の乱』(永享9年・1437年)では、持氏が自害し、宅間上杉氏も滅亡。『結城合戦』(永享12年・1440年)では、持氏の遺児を奉じた反乱が鎮圧され、山内・扇谷両上杉氏が台頭した。
この時期、関東は公方と管領の二重構造のもとで、幕府の意向と地方勢力の利害が交錯し、政治的安定を欠いた状態が続いていく。
● 古河・堀越・小弓公方の分立:関東の三公方体制と内乱の激化
鎌倉公方・足利成氏が『享徳の乱』(康正元年・1455年~文明15年・1483年)を起こし、鎌倉から古河へ拠点を移して『古河公方』を名乗ると、足利政知はその討伐ために幕府公認の鎌倉公方として下向するが、関東の混乱および幕府権力の衰退と上杉氏の内紛などで鎌倉に入れず、手前の伊豆の堀越に留まり、『堀越公方』と称される。
一方、成氏の孫にあたる足利義明は独立して千葉県小弓城に入り『小弓公方』を名乗るなど、関東は三公方に分裂し、更に混乱を極めた。
この分裂により、関東は、古河公方・小弓公方・山内・扇谷上杉氏の四勢力が対立。『長尾景春の乱』(文明8年・1476年)では、景春が鉢形城を拠点に反乱を起こすが、太田道灌が鎮圧。
道灌は扇谷上杉氏の家宰として活躍し、主家を上回る実力と名声を得るようになると、主君である上杉定正に謀反を疑われ、暗殺されてしまう。その後、『長享の乱』(長享元年・1487年)が勃発し、山内・扇谷両上杉氏が激突。関東は内乱の連鎖に陥り、幕府の統制力は著しく低下した。
● 伊勢新九郎(通称:北条早雲)の登場と伊豆・相模平定:戦国大名の原型
伊勢新九郎盛時(伊勢宗瑞、通称:北条早雲)は、今川家当主・義忠の死後に起こった家督争いに介入し、甥である龍王丸を擁立して今川氏親とし、駿河国内の混乱を収めた。
その後、幕府の命を受けて伊豆の堀越公方・足利茶々丸を討伐し、伊豆国を平定。更に、明応地震による混乱に乗じて、小田原城を無血で奪取することに成功した。これにより、後の北条氏の本拠地となる小田原を手中に収める。
山内荘や本牧郷なども戦わずに領地化し、戦闘を最小限に抑えながら勢力を拡大した。玉縄城でも扇谷上杉氏を破り、新井城にて三浦一族を滅ぼすことで相模国の支配を確立。これらの一連の戦いを通じて、関東における新興勢力として台頭した。
宗瑞は、家臣団の編成や法制度の整備など、領国支配の近代化を進めた点でも注目される。その統治スタイルは、後の戦国大名たちのモデルとなり、戦国時代の政治・軍事のあり方に大きな影響を与えた。
● 小田原北条氏の隆盛:河越夜戦での勝利
宗瑞の死後、嫡男の氏綱が家督を継ぎ、武家政権を確立した執権・北条氏にあやかって『北条氏』を名乗るようになる。支配領域を武蔵国にまで拡げるが、氏綱も天文10年(1539年)に死去したため、嫡男の氏康が小田原北条氏の家督を継ぐ。
その氏康は、今川義元・武田晴信(信玄)との対立を深め、天文14年(1543年)には義元が伊豆方面へ侵攻し、同時に河越城が古河公方・山内・扇谷上杉氏の連合軍8万に包囲されてしまう。氏康は晴信の仲介で今川と和睦し、西方の危機を回避。氏康は8千の兵で夜襲を仕掛け、義弟・綱成が籠る河越城を救うとともに、扇谷上杉氏を滅ぼし、古河公方を降伏させた。世に云う『河越夜戦』である。
● 戦国関東の継承と断絶:中央の政変も大きく影響
越後守護・上杉定実の死去により、家宰・長尾景虎が後を継ぎ、関東管領職を譲られて上杉政虎(のち輝虎、謙信)と改名。北条氏康は武蔵・上総・下総へ進出し、謙信との対立が激化した。
これに対し、氏康・義元・晴信の三者は天文23年(1554年)『甲相駿三国同盟』を結び、相互不可侵を維持。義元は織田信長との戦いに集中するが、桶狭間の戦いで討死。信玄は同盟を破棄し、徳川家康と連携して駿河へ侵攻。信玄の死後、氏政と家康は同盟を結ぶ。
天正10年(1582年)、武田氏滅亡後に本能寺の変が起こり、家康は甲斐・信濃の支配を目指す。真田昌幸が上野へ侵攻し、氏政と家康はまたも対立するが、再び和睦した。
● 小田原の終焉、江戸の胎動:北条氏滅亡と家康の関東構想
その後、宇都宮・佐竹氏らが反北条勢力として連携。氏政は家康に援軍を要請。秀吉の調停により氏直は臣従の意を示すが、名胡桃城を奪取したことで秀吉と決裂。
天正18年(1590年)、秀吉による小田原攻めが始まり、北条氏政・氏照は切腹、氏直は赦免され高野山へ。北条氏は河内狭山藩として幕末まで存続。
小田原北条氏滅亡後、家康は関東へ入封。旧北条家臣を召し抱え、道路の再整備や利根川東遷事業、鎌倉の寺社再建など、関東における都市基盤の大改造を行った。これが後の江戸幕府成立と江戸発展の礎となる。
講演後記
NHK大河ドラマでは、室町末期の戦国時代を取り上げた作品は数多くあるが、室町時代そのものを主軸にした作品は『太平記』と『花の乱』の2作だけ。これは、室町時代が視聴率を取りにくい時代背景であり、政治構造や人物関係が複雑で、視聴者にとって非常に分かりにくいことを証明している。
今回の講演では、その分かりにくい(複雑かつ登場人物多し)室町時代の関東争乱について、相澤先生ならではのユーモアを交えた語り口調で、分かりやすくご講演いただいた。
講演を通して、その根底には、歴史を分かりやすく伝えていくという『歴史水先案内人』としての先生の自負が感じられ、我々歴史の会としても見習わなければならないと感じた。
相澤先生、誠にありがとうございました。次も、『分からない?』シリーズでのご講演を宜しくお願いいたします。

黒板を駆使し、熱意を込めて講演される相澤先生